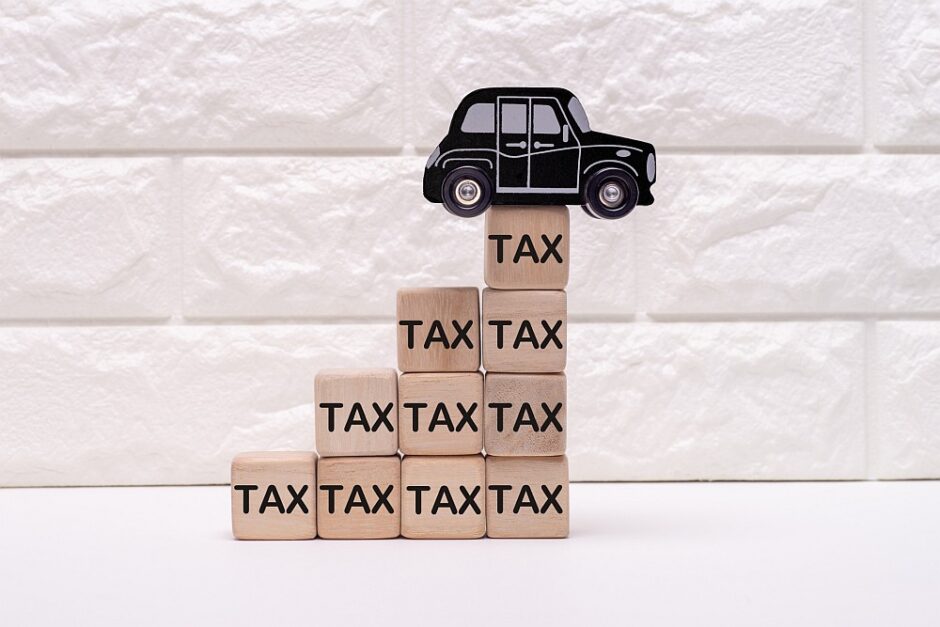国会で国民民主党の榛葉幹事長が自動車関連税について質問をしていました。
「ヘリコプターや船は消費税だけで買えるのに、なぜ車だけ “9種類以上の税金” を取られるのか?
という疑問が、SNS・掲示板・ニュースで大きな話題になっています。
自動車は日本全国で必需品であるにもかかわらず、購入から廃車まで一貫して複数の税が課され、総税収は年間約9兆円規模 と言われています。
本記事では、そんな「自動車関連税 9種」をできるだけ分かりやすく整理し、さらに「なぜ車だけ重税なのか」「今後どうなるのか」を分かりやすく解説していきます。
自動車にかかる税金は「9種類以上」
自動車にまつわる税金は、ざっくり分けると以下の 9 種類があります。
(1)自動車取得税の代わりとなった “環境性能割”
(2)消費税(購入時)
(3)自動車税(種別割)
(4)自動車税(軽自動車税)
(5)自動車重量税
(6)ガソリン税(揮発油税)
(7)石油税
(8)走行時の “税の二重取り” と批判される暫定税率分
(9)高速道路の利用で発生する “道路関連の上乗せ料金”
(※厳密には道路特定財源から一般財源化された部分も含む)
細かく分類すれば 10 種以上にもなるので、「日本は車に世界一厳しい税体系」と言われる理由はここにあります。
新車・中古車の購入時にかかる税。燃費の良し悪しで税率が変わる「購入時課税」のひとつ。
- 税率:0〜3%
- ハイブリッド車やEVは非課税〜軽減
- ガソリン車は1〜3%が一般的
ヘリコプターや船は「消費税だけ」ですが、車は これに加えて複数の税 が上乗せされます。
毎年必ず払う“固定資産税のような税”。排気量で税率が決まる。
- 13年経過すると “重課” により増税(約15%増)
- 「長く大切に乗るほど増税」という逆インセンティブが批判されるポイント
軽自動車にかかる固定税。普通車より安いが、13年経過後はやはり増税(約20%増)。
車検時にまとめて払う税。車の重さが重いほど税額が高い。
- 13年超 → 大幅に増税
- 「18年超」でさらに重課
- 環境負荷が理由とされるが、EV や HEV でも重課されるため論理性に疑問の声
ガソリン1Lあたりに課される国税。しかも その上に消費税がかかる “税金への消費税” が存在する。
一般的に “二重課税の象徴” と批判される税。
燃料に含まれる別の税。ガソリン税と合わせると、1Lあたり約53.8円が税金と言われる。
本来は時限措置だった“上乗せ税率”。道路整備のためとして長年続いている。
実質的には「恒久的な増税」と化していると批判され、2025年12月31日で廃止が決定(軽油は2026年4月1日)
高速道路料金には、道路整備費用や様々な上乗せが含まれる。「税金による道路整備+高速料金の二重課金」との声も多い。
国・自治体の資料や業界団体の試算を合計すると、自動車関連税は年間 8〜9兆円 と言われる巨大財源です。
これは国家予算の約10%近くに相当するレベルで、自動車ユーザーが“日本経済の太い柱”になっている状態です。
なぜ車だけ「異常に税金が多い」のか?
理由は大きく3つあります。
① 車は「量」が多いので確実に税収が取れる
日本の自家用車保有台数は約8,000万台。固定的に安定した税収源。
答弁の中で、片山財務相が「取れるところから取る」という発想であったことを認めています
② 旧来の道路財源制度の名残
道路整備のための税体系(揮発油税など)が一般財源化した後も“税だけは残った”状態。
③ 新車販売を促す仕組み
- 13年超の“重課” → 愛車を大切に長く乗りたいというユーザーには理解できない
- 環境性能割の減税基準
- エコカー減税制度
これらは新車への買い替え促進効果があるため、
政治的に維持されやすい。
特に批判されているポイント
● 長く乗るほど増税になる(13年・18年重課)
環境のためと言いつつ、「新車製造時の環境負荷」の大きさは無視されている。
- GR86 の通常の自動車税(13年未満)は、2.4L 区分で 約 45,000円/年
- 経過年数 13年超での重課後 → 約 +15% → 約 51,700円/年
税額は車両重量によって決まる。GR86 の重量(約1.26–1.29t)は「~1.5t」の区分に収まります。
| 経過年数 | 2年ごとの重量税(目安) | 年換算 |
|---|---|---|
| 13年未満 | 約 24,600円/2年分(=12,300円/年) | 約 12,300円/年 |
| 13年超(重課後) | 約 34,200円/2年分(=17,100円/年) | 約 17,100円/年 |
| 18年超(さらに重課) | 約 37,800円/2年分(=18,900円/年) | 約 18,900円/年 |
※上表は、一般的な「エコカー減税の対象外」「本則税率」の普通乗用車としての標準税率を前提としたもの。
| 状態 | 年間合計税負担の目安 |
|---|---|
| 13年未満 | 約 57,300円/年(自動車税 45,000 + 重量税 約12,300) |
| 13年超 | 約 68,800円/年(自動車税 51,700 + 重量税 約17,100) |
| 18年超 | 約 70,600円/年(自動車税 51,700 + 重量税 約18,900) |
増加幅の目安
- 13年超 → 年間で約 +11,500円
- 18年超 → 13年未満と比べて年間で約 +13,300円
- GR86 のような比較的小さめ・軽めの普通車であっても、13年超以降は税金だけで年間1万円以上、10年で見ると数万円の追加負担になる。「長く大事に乗る」ほど税負担が増える構造が確かに存在する。
- ただし、重量が軽めの車なら「重量税の重課による跳ね上がり」は過度に大きくない。「大型ミニバン/SUV/2t級以上の重量車だと、増税のインパクトはもっと大きくなる」であろう。
- つまり、こうした重課の制度は「大排気量・重量車優遇 → 小型軽量車にも負担の重さを一定維持 → 新車/買い替え促進」という政策効果狙いがあるが、スポーツカーや軽めの普通車オーナーには「長く乗ってもあまり報われない」構造とも言える。
● 燃料税に消費税がかかる“二重課税”
ガソリン税→さらにその上に消費税、という構造に強い不満。
● 9種類もある複雑な税体系
一般ユーザーが理解できないほど複雑。一般財源化した部分は税金が何に使われているか不透明。
AI:今後どうなる?(憶測と希望)
現状の空気感からすると、次の流れが想定されます。
【1】13年重課の見直し(議論が活発化)
環境負荷の観点からも合理性が薄く、「長く乗るほど増税」は国民の不満が最も強い部分。
政治家の発言・国会質問でも取り上げられ始め、まずここが廃止・縮小の候補。
【2】ガソリン税の二重課税問題は長期戦
財源規模が巨大なため、近いうちに解消する可能性は低い。
ただし EV への移行でガソリン税収が減るため、将来は代替税の可能性あり。
→走行距離課税は検討なしとの答弁がありました。
【3】税体系の簡素化(統合)が議論される可能性
国民からは「多すぎて訳が分からない」という声が強く、税の一本化(環境税+走行税など)は長期的に検討が進むと見られる。
まとめ:自動車関連税は“世界的に見ても異常に多い”
日本の車ユーザーは、次のすべての段階で複数の税を負担し、その総額は年間約9兆円。
- 購入
- 所有
- 走行
- 車検
- 燃料
環境や道路整備という名目がある一方で、制度の複雑さ・過剰さ・重課の矛盾 が国民の間で強い違和感を生むようになりました。
今後は次のような議論が活発化することが望まれます。
- 13年重課の見直し
- 税体系のシンプル化
- EV時代の新たな税収モデル
高市政権が発足し、決断力と機動力が高い支持率を支えています。
SNSによる情報の拡散が国政への興味・関心を高め、それに伴ってこれまでの矛盾や非効率に厳しい目が注がれるようになりました。
自動車関連の負担を軽減し、自動車を取得しやすい環境を作ることが、日本の最も大きな基幹産業を支え、それが国力を高めることにつながるのではないか、と強く思います。
 Intelligence-Console
Intelligence-Console